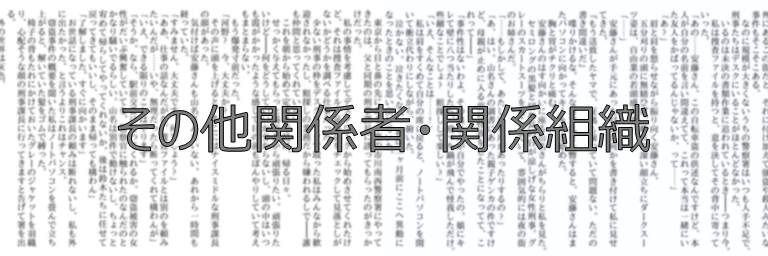目次
警察関係者
警察職員
庶務課や経理課等にいる事務職員は警視庁/都道府県警察という役所に務める地方公務員という扱いになります。そのため正確には警察官ではないため、階級はなく、ガサや逮捕等の警察官としての職務行為は遂行できません。
事務職員とはいえ警察の仕事に関する基礎知識や心構えが必要になるため、採用後は警察官と同じように全寮制の警察学校に入学し約1ヶ月間の研修を受けます。
交番相談員
元警察官が非常勤の公務員として採用され、交番勤務の警察官がパトロール等で不在のさいに駐在して、道案内や住民の相談等を受け付けたりしています。
制服は警察官のものと異なり、胸のところに「交番相談員」という標章をつけています。
- 交番相談員について
- 警察官ではないため取調べや職務質問、巡回連絡等は行いません
- 以前は被害届も受理できなかったようですが、現在は「被害届の代書・預かり」という形でシンプルかつ件数の多い罪種について、実質的に被害届を取り扱うことができるようになったそうです
- 同様に警察官しかできない「物件事故報告書の作成」についても「物件事故報告書の作成補助」という形で、一定の制約下で可能となったようです
警察犬
警察犬は人間の約6,000倍と言われるその鋭い嗅覚を利用して、逃亡した被疑者の追跡や麻薬が隠されている場所、証拠品の収集等で活躍しています。
警察犬には警察が飼育・訓練をしている「直轄警察犬」と、民間人が飼育・訓練をして審査に合格した「嘱託警察犬」の2種類があります。
警察犬の任務は主に以下のような内容です。
- 足跡追及活動
- 事件現場に残された被疑者の持ち物の臭いを手がかりに逃走中の被疑者の足取りを追います
- 臭気選別作業
- 現場に残された遺留品と被疑者の臭いを嗅ぎ比べて同一人物かどうかを特定します(裁判でも証拠能力として認められているそうです)
- 被疑者の遺留品の原臭を布切れに移し、選別台の上に予め番号札を振ってスペースを用意し、被疑者に臭気選別について説明した上で布切れをどこに置きたいか決めさせます
- 被疑者が選んだもの以外の番号札のスペースに他人の臭いをつけた布切れを置きます
- 警察犬に遺留品の原臭を嗅がせ、選別台から同じ臭いの布切れを持ってこさせます
- 臭気選別の対象が5つあるとして、正解が3番の場合、1から順に嗅いでいって5まで嗅いだ上で3番を持ってくるのは無効になります
- 1から順に嗅いでいって3番目でその布切れを持ってこないといけないそうです(証拠として役に立たないため?)
- 犬種は以下です
- 鑑識犬
- 麻薬捜査犬
- 警備犬
- 災害救助犬
- 極左犬(公安が使っているそうです)
- 定年は概ね10歳で数頭しかいないため休日はほとんどないそうです
普段は訓練所にて24時間待機しながら、事件が発生し出動要請を受けると車に乗せられて出動します。
以下が警察犬の一日です。
| 時刻 | 内容 |
|---|---|
| 6:00 | 起床・排便(自主的に自分の部屋からトイレまで行き用を済ませて戻ります) |
| 7:00~10:30 | 訓練(朝一の訓練が行われます) |
| 11:00 | 朝食(栄養バランスが考慮された食事を採ります) |
| 12:00 | 犬舎清掃(担当者が掃除をします) |
| 13:00~16:00 | 訓練・犬の手入れ(健康チェック) |
| 16:00 | 夕食 |
| 17:00 | 排便 |
| 19:00~20:00 | 夜間訓練(夜間の出動に備えた訓練) |
| 20:00 | 排便 |
| 21:00 | 就寝 |
警察犬の活躍例
- 2011年、東京都羽村市で発生した人質立てこもり事件にて警視庁刑事部鑑識課の警察犬が人質の女性が監禁されている部屋を臭いで突き止め、別室にいる被疑者の部屋にSITが突入し解決に繋がりました
- この警察犬は人間が死亡しているかどうかが分かる臭気選別の訓練を受けていたそうです
警察犬あるある
- 警察犬は車に乗せられて出動しますが、ほとんどの犬は車酔いをするそうです
- そのため現場についても30分程度休ませる必要があります
- ある事件で警察犬を呼ぶことになって期待したものの、車に酔って吐いてしまい全く役に立たなかったケースもあったとか
- 行方不明者の捜索で山中に入り足跡追及活動をさせようとしたものの、久しぶりの野山にテンションが上がって全く役に立たなかったことも
関連組織
法科学鑑定研究所
科学捜査研究所のOBを中心に組織された民間の鑑定機関(株式会社)で、刑事・民事裁判での証拠の鑑定を年間100件以上扱っています。
- 刑事事件では事件解決に貢献しています
- 交通事故等で警察が立件を見送ったものについて交通事故鑑定もしています(たまにテレビでドキュメンタリーが放送されています)
- 映画やドラマにおける科学捜査シーンの監修や取材協力にも携わっています
警察病院
元々は警察職員やその家族に対する診療を行う病院として設立されたものの、現在では一般人にも利用を開放している病院です。開設者は警察の外郭団体である一般財団法人や警察共済組合であるため、民間の病院となります。
東京都には中野区の東京警察病院があります。
凶悪事件・重要事件の被疑者が受傷・病気で運ばれるのが警察病院となり、そうでもない被疑者の場合は他の病院に運ばれるそうです。
メディア
新聞・テレビ・通信社はそれぞれ警察担当を置いており、中でも警視庁刑事部に対しては記事になる事件が多い関係で多くの人員を割いています。
- 人員配置
- 捜査一課・三課に3人ずつ
- 大事件を担当するのは捜査一課担当、略して一課担(イッカタン)
- 捜査二課に2人
- 生活安全部担当に1人
- 警備・公安担当に1人
- 捜査一課・三課に3人ずつ
現場に真っ先に到着するのは記者クラブ加盟メディアの報道部門です。テレビ局の場合はワイドショーとは別部門のため取材できません。
- 現場への駆けつけ
- 現場では「報道」の腕章をつけて取材します
- メディアの「前線指揮車」(マイクロバスを改造した車両)がある場合、それは大事件か長期化する事件になります
警察は被疑者逮捕や重要事件発生のタイミングで必要があれば、警察本部や所轄警察署で記者会見を行います
- 記者会見について
- 記者クラブでは定例の記者会見も行われています
- 警察本部では課長クラスが、所轄署では副署長が広報します
- 警察がメディア対応するのは記者クラブのみです
- 基本的には逮捕されてから数時間後にその事実が発表されます
- タイミングによっては名前が分かったり分からなかったりするそうです
- 中には送致や起訴のタイミングもあるそうです
- 記者クラブでは定例の記者会見も行われています
地方公務員法によって、警察官個人はメディアに対しては元より自分の家族に対しても自身が知りえた事件・捜査について話してはいけない規則になっています。
- しかしこれは建前であって、記者と個人的に情報交換をしていることもあるそうです
記者会見
ドラマ等で見かけるような、記者会見している警察官に対して記者たちが詰め寄るようなシーンはほとんどないそうです。殺人事件であれば被害者の年齢や亡くなっていた場所、司法解剖が済んでいれば死因といった基本的な情報を発表し、それをお記者たちが大人しく聞いているという図式です。
- 捜査本部が立つような事件であれば、最初の頃は1日1回は記者会見を開くそうです
- 情報は小出しにして「警察の頑張っている」感を出すため
- 記者会見では多くは語らず、時には捜査のために嘘をつくこともあるそうです
- 「被疑者の目星は立っていない」と嘘をついた場合、実は被疑者が判明していてそれを張り込んでいる捜査員たちに対し、その被疑者がボロを出すかもしれないため
この時点で細かく聞いたとしても捜査情報のため誤魔化されたり嘘をつかれてしまいます。仮に教えてもらったとしても他メディアの記者たちも聞いているわけで、自分のメディアだけが得たスクープにはなりません。
ここからが記者たちの腕の見せ所になります。夜討ち朝駆けして捜査一課長や捜査員たちから情報を得てスクープにつなげていきます。
記者クラブ
一般的に「記者クラブ」とは公的機関への継続した取材を目的として大手メディアが数社集まって結成した民間の任意組織で、官公庁の組織ではありません。
加盟報道機関は持ち回り制で記者クラブの幹事社を務め、記者クラブの運営を行っています。
警視庁/道府県警察本部の広報課は記者クラブの幹事社に対して記者会見の連絡をし、幹事社が記者クラブ加盟報道機関各社に連絡をして記者会見に参加(または記者クラブが記者会見を主宰)し、そこで得た情報を自分たちのメディアを通じて報道しています。
- 広報課が記者会見を開くのは事件発生時と被疑者逮捕の2回程度
- 記者クラブには様々な問題が指摘されています
- 記者クラブ側が記者クラブ加盟社以外の記者会見参加を認めない、記者クラブへの加盟申請に対して加盟社のうち1社でも反対があれば断られる等、記者会見の独占と報道の閉鎖性が指摘されています
- 警視庁/道府県警察本部側が記者クラブ加盟社の記者が常駐できるよう記者室を用意しており、便宜供与に当たるのではという批判もあるそうです
- 記者室には記者用のロッカーやテーブル、通信機器等も用意されたりしているようです
- 広報課からの連絡を受ける等、取材対象からの協力を得ての取材であるため記者の取材能力の低下も指摘されています
- 警視庁/道府県警察との馴れ合いも指摘されています
警視庁には現時点で3つの記者クラブが存在しています。
- 七社会
- 朝日・毎日・読売・東京・日経・共同通信の6社が加盟しています
- 以前は時事新報も加盟していたが休刊したため6社になった経緯があります
- 警視庁記者倶楽部
- NHK・産経・時事・ニッポン放送・文化放送・MXTVが加盟
- ニュース記者会
- 日本テレビ・TBS・フジテレビ・テレビ朝日・テレビ東京が加盟
記者クラブ加盟各社から7~10名程度の記者が常駐しており、捜査一課・捜査二課・警備・公安等、警視庁の担当部門ごとに記者を配置しています。
各担当記者はチームを組み、リーダーは「仕切り」、次が2番機、次が3番機と呼ばれています。
- 戦時中の飛行隊の名残で、基地に帰還する順番の名前だそうです
- 3番機は1番最後に帰るため若手の新人記者が務めるそうです